はるみ代表と個人LINEをしていて、ひょんなことからTi主機能の人(INTP、ISTP)が、Tiを正しく使えている状態についての話になりました。
なんともTiが正しく使えていると”失敗を恐れない”とのことでした。
最初はどういうことなのかよくわからなかったのですが、以前認定コースにて頂戴したテキストを読み返したところ、腑に落ちました。
Tiとは例えるなら理科の実験のような機能です。8つある心理機能の中で、最も科学的な機能とも言えるでしょう。
実験や科学には失敗がつきものです。一つ一つ条件を変えて、”ああでもない。こうでもない。”となりながら、分析と検証を繰り返して真理を追求していくのです。
つまり失敗は正しさを導く素敵な材料となります。
そうなると確かにTiが正しく使えていると”失敗を恐れない”状態となるはずです。
そして私はこの気づきと共に、1つの着想を得ました。
それは人とコミュニケーションを取る時に、この分析と検証を出来ないかというものです。
特に現在進行形で会社で新人教育に携わる立場になったからこそ、この実験を行う価値があると感じました。
これまでタイプを学んで、自分自身がTeやFe、Seといった機能が苦手という自覚がありました。
ただ新人教育を行うにあたっては、これらの機能を使わないとならない場面が少なからずあります。
そこで苦手なりにまずはやってみて、相手の反応を見て、反応や成果が芳しくない場合は何がよくなかったのかを検証しました。
逆に反応が良かった場合も何が良かったのかを自分の中で検証しました。
すると意外と、そもそも以前にも記事にした、Fiモードで話を聞けていない自分がいることに気づきました。
そして新人の価値観や不安な気持ちを否定せずに聞くということを意識しました。そしてそのあとにTe的な厳しめの指摘をマイルドにしてみるとうまくいきました。
そして結果として新人から一定の信頼を得るに至りました。
いい結果に至れたのは、Fiをエッセンスに使ったからですが、そのもっと根本に自分と相手のコミュニケーションを検証をするという、Tiの力があったからだと思います。
また、この自分と相手のコミュニケーションを検証するスタイルは、Ti主機能にとって大きな可能性を含んでいると感じました。
Ti主機能の人(INTP、ISTP)と話していると、頻繁に”他人に興味ない”や”人間が嫌い”、”人間が怖い”といった言葉が出ます。
それはおそらくコミュニケーションを、Fの機能のみで成り立つものと捉えているからではないでしょうか。
でも意外とそうではありません。
相手といい関係を気づくには、むしろTiこそ重要です。
適切に”ここではFモード、反対にこういう時は毅然とTモード”といった具合に、分析と検証をしないとならないからです。
そして仮に失敗したとしても、いい反省材料として次に活かして検証していくのもTiです。
主機能をコミュニケーションでも活かせると、これまでにない楽しい経験ができるのではないかと思います。
文・池田 美沙子
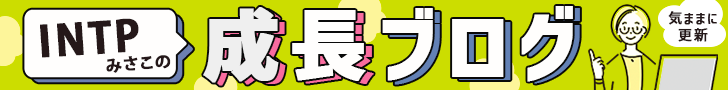
イベント情報はこちら→イベント案内
公式LINEにて情報発信中!→https://lin.ee/2iexXD130

